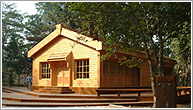本実験林は、教育実習、試験研究、生態保護、モデル経営を目的としているため、今期経営計画書の経営期間(1998~2008年)は、世紀を跨ぐ森林生態系理念に基づいて、教育実習と試験研究を計画し、生態ランドスケープの充実性を考慮し、森林生態系の種多様性と遺伝的多様性を守り、固有種と動植物の生息地を保護するとともに、管轄区内における地域社会の要求と環境倫理の価値と融合することで、森林資源経営が生態系において永遠に発展し、多目的経営の機能を発揮して、本実験林におけるモデル経営の成績を明らかにしなければならない。
| 林業経営が正に転機を迎え、政府の組織再編に乗じて、本実験林も人的物質的財産を積極的に改めて整理し、結束力を発揮し、「ビジネス生態系」を主要理念とし、生態保全と森林生態系の持続的な発展を重要と考える。また、将来における行政法人化のため、本実験林の「組織評価」を積極的に押し進めるとともに、「台湾大学実験林白書」及び「台湾大学実験林年報」などを刊行し、多くの人に本実験林を一層理解してもらい、林業経営が多くの人から注目と支持が得られることを目指す。 本実験林の第8期経営計画は、2008年に十年計画が満期するため、現在積極的に「第9期経営計画書」の編成を行っている。これ以外にも「対高岳クスノキ神木における自然保護区」と「対高岳経営林区整備測量」などの専門議案が計画進行中である。
|
| 本実験林管轄内で、現存する崩壊地及び崩壊恐れのある危険区域を調査し、情報空間システムの資料を構築する。実施の軽重や緩急にかかわらず、毎年予算を計上することで、崩壊地の回復、崩壊拡大及び災害発生の回避をするとともに、経費を積極的に工面して崩壊地の根幹整備を行う。 921地震とトラジ台風の災害後、本実験林の治山治水作業は自然生態による工法を益々重要視している。現地の原料や建材による構造方法を利用することで、斜面と渓流周辺における自然形態システムの保全と、景観保護に留意することができる。 |
| 行政院における行政作業のe化政策に適応するために、ソフト・ハードの更新と開発を積極的に取り組んでいる。ハードにおいては、パソコン利用が普及し、民国95年(2006年)末までに、本実験林はパソコン155台を設置、その内、本管理所には82台設置され、人とパソコンの比率は約1:1となった。現在もなお、パソコン設置数を増やしている。インターネットも、サーバーを5台配置し、主に、地域とのネットワーク構築から、各経営林区のネットワークも、インターネットによって構築されている。 |  » 公文書ファイル資料の構築 |
|
| ソフトの設備では、業務の必要に応じて随時更新、またはソフトを新規購入し、国内の関連部門と相互にデータを提供している。また、民国89年(2000年)から、地理データシステムと関係するソフト・ハードの使用を開始し、本実験林におけるデータバンクの構築に着手しており図表データの整備し、林地の経営管理と方策支援のサポートを行っている。 また、業務の必要性から、本実験林に適用するシステム開発の計画も持ち上がっており、実用化に向けて、民国95年(2006年)末、製作と管理システムのネットワーク化を、実験林の公式文書で取り決め、データと林業の実務を一体化させ、効果の向上を図っている。さらには、本実験林におけるグローバルな情報ネットの内容を随時更新させ、豊富な林業データや便利なサービスを提供するとともに、多くの人々とのコミュニケーションの場を構築していく。 |
||
| 造林作業は永続的な森林資源の保全における根幹である。1997年より、「国民造林運動要綱および実施計画」に伴い、毎年10数万株の苗木を国民造林運動に提供するとともに、921地震や台風トラジの災害で崩壊した区域に対して、新たに造林を行っている。現在造林業務は、造林の継続と森林の育成、天然林の保全以外にも、人工造林の強化を図り、2001~2007年までに、毎年平均で約42.61ヘクタールの造林を行った。各区における樹種を、主に原生樹種に改めることで、森林の持続的な経営を目指している。それ以外にも、大量のエコガーデニング苗木を育て、学校、機関、地域、公園、国有林班に提供し、林地の拡大と、同時に、相互の親睦を深めることを実現させている。 |
育成作業は林を育てる段階の重要な業務である。苗木の新植、改植、補植が適切に行われなければ、造林作業は無駄になる。造林作業の内容は、除草、下刈り、枝打ちと育成期間の間引き、以上の4項目である。異なった林区分の樹齢ごとに、育成作業の内容が異なってくる。本実験林は適切に樹種を育てることを考慮するだけでなく、林区分の育成作業と林地の養分管理を強化することで、成熟樹木を予定蓄積量まで増やし、持続的に、経営原則や生態保全の目的を達成している。
|
| 森林法と森林保護規則に順じて、本実験林における森林保護管理業務の要点と、保護管理作業における抜き取り検査の実施・細則を取り決めている。各経営林のスタッフが、林地においてグループで巡視を強化することで、盗伐や無闇な開墾の発生を防ぐとともに、森林火災の防止と撲滅、天然災害の報告、森林病虫獣害の発生防止、などの強化を可能にする。 |
| 地域の林業普及に向け、相互の親睦を図るため、2003年1月から、行政院農業委員会林務局と協力して「地域の林業─住民による保全と共存計画」を推進するとともに、「地域の林業─住民による保全と共存計画講習会」を積極的に開くことで、地域住民へ森林保全計画の参加を促している。 |
森林レクリエーションは森林経営の一環であり、森林多目的経営の一つである。国民が持つ屋外の活動場所の需要や、政府が推し進める観光事業の拡大など、社会全般の要求に本実験林を適応させるために、屋外活動、生態教育、健康レクリエーションの場を国民に提供し、森林多目的経営を積極的に展開している。また、社会からの要求に応じて、自然教育と保全活動も強化している。
|
| 本実験林の構造と様相は、良質な造林面積が非常に広大で、一部の造林地は辺境な場所にあるため、火災防止に特に気を使い、その宣伝活動にも特別力を入れている。実際の森林火災発生時に森林資源を守るために、迅速に火災現場に人を動員し消火に当たることができるよう、現在、スタッフ全員が森林火災撲滅チームに参加し、消火訓練を実施している。 |
| 本実験林には水里郷永豊村に木材利用実習工場を設けており、学生に教育実習の場を提供するとともに、学校用の勉強机や椅子、小中径木材を応用した家具などを製造し、木製品や工芸品などの開発利用とその推進を行っている。 |